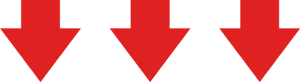「消費税」とは?課税業者を選択する節税スキーム
消費税の節税を取り組むにあたって、まずは消費税とはどのようなものか理解しておく必要があります。
原則として、消費税の納税義務がある課税事業者は法人だけではなく、個人事業者においても対象となります。
状況によっては、課税事業者を選択したほうが、有利になるケースもありますから順番にご説明していきましょう。
事業者が納税する消費税
消費税とは、商品やサービスなどの消費に対して公平に課税される間接税のことを指しています。
あらゆる商品や製品、サービスの提供など、幅広く課税の対象とされています。
消費税の負担は、事業者が提供する商品やサービスを消費し提供を受ける消費者であって、納税義務者となっている事業者が納付する仕組みになっています。
消費税の納税義務者である課税事業者とは
- 法人:前々事業年度における課税売上高が1,000万円を超えている
- 個人事業者:前々年における課税売上高が1,000万円を超えている
消費税の納税義務があるかどうかについては、上記の通り、課税の基準期間の課税売上高(消費税の課税対象になる売上高)によって判断されることになります。
課税期間は法人と個人事業者によって異なっており、法人は事業年度、個人事業者は暦年となっています。
また、課税の基準期間は、法人では前々事業年度、個人事業者は前々年と、2期前の課税売上高が1,000万円を超えている場合に、消費税の納税義務があるのです。
例えば、法人の場合で言えば令和3年度の申告であれば基準期間が「令和元年度」となり、個人事業者であれば「令和元年」となるのです、
その期間の課税売上高が1,000万円を超えているのであれば、納税義務があり課税事業者となります。
消費税の納税義務がある課税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていない場合)
上記において、2期前の課税売上高が1,000万円を超えている場合に納税義務がある課税事業者になるとお伝えしました。
ただし、いくつかのケースに該当する場合には、1000万円を超えない場合においても課税事業者として判断されることになります。
- 資本金1,000万円以上の法人を設立したとき
- 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合
- 特定期間における給与支払額が1,000万円を超えた場合
- 課税事業者となることを選択した場合
- 課税売上高が5億円を超える法人から50%を超える出資を受けているとき
資本金1,000万円以上の法人を設立したときには、税務署に対して「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出し、課税事業所として扱われることになります。
また、特定期間の課税売上高もしくは給与支払額が1,000万円を超えた場合においては、基準期間における課税売上高が1,000万円を下回っているとしても、その課税期間においては課税事業者となります。
「特定期間」とは、法人の場合はその事業年度の開始から6か月間、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日となっています。
また、課税事業者になるほうが得になるケースがありますので、自ら課税事業者となることを選択することができるようになっています。
課税業者を選択して有利になるケース~「消費税の還付」
- 輸出業者のように売上の大半が免税取引の場合
- 多額の設備投資が必要となる場合
- 経費による出費が多額となり、当分は赤字が予想される場合
消費税の納税義務ではない事業者であっても、課税事業者を選択したほうが有利になるケースがあります。
それは、売上高に対する消費税よりも、仕入などにかかる消費税額のほうが大きいような場合です。
そのようなケースの場合には、その差額が還付されることがあるのです。これを「消費税の還付」と呼んでいます。
例えば、輸出業者の場合、海外企業などに対して販売するわけですから、その製品者サービス対して消費税はかかりません。
しかし、仕入れを行う場合には消費税がかかってしまうことになります。
そのようなケースであれば、仮に免税事業者であるとしても、課税対象者となっていれば消費税の還付が受けられますから、有利になることが多いのです。
そのため、上記のようなケースが考えられる場合には、課税事業者を選択しなければなりません。
免税事業者が課税事業者を選択するには
免税事業者が課税事業者を選択する場合には、税務署に対して「消費税課税事業者選択届出書」を提出することになります。
消費税の税額を計算する方法は、「簡易課税方式」でなく「原則課税方式」を選択していることが大切です。
「原則課税方式」とは、課税期間中の課税売上に対する消費税額からその期間の仕入れなどに対する消費税額を差し引いて消費税額を計算する方法のことを指しています。
この方法を選択する場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する際に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して「原則課税方式」を選択しておくようにします。
ちなみに「簡易課税方式」とは、課税売上に対する消費税額に一定の「みなし仕入率」を掛けて納付する消費税額を計算するというものです。
ただし、免税事業者が課税事業者を選択する場合には2年間は免税事業者に戻ることができません。
そのため、今後のことを見極めたうえで、選択するのかどうか判断することが必要となります。
消費税の計算方法をうまく活用した節税スキーム
納税義務のある課税事業者が消費税額を計算する方法として、「原則課税方式」「簡易課税方式」の2種類があります。
この計算方法は、どちらを選んでも構わないのですが、上記でも説明した通り、選択を間違ってしまうことによって税額が大きく変わってしまい不利になってしまうことがあります。
そのため、計算内容をしっかりと把握したうえで、どちらを選択するとベストなのか注意することが大切です。
原則課税方式とは
実際の計算式としては、下記のとおり行います。
- (課税売上高×7.8/110)+(課税売上高×6.24/108)=売上税額
- (課税仕入れ高×7.8/110)+(課税仕入れ高×6.24/108)=仕入れ税額
- 売上税額ー仕入れ税額=消費税の納付税額
軽減税率の適用対象となる取引については「6.24/108」を乗じた金額となっています。
売上のすべてが課税売上となる場合には計算はスムーズに行えますが、非課税取引が含まれている場合には、事務作業が煩雑になってしまうといったデメリットがあります。
簡易課税方式とは
「簡易課税方式」とは、課税期間中の課税売上にかかる消費税額に対して、事業区分に応じた「みなし仕入れ率」をかけて計算する方法のことを言います。
計算は下記の通りとなっています。
実際の計算式としては、下記のとおり行います。
- (課税売上高×7.8/110)+(課税売上高×6.24/108)=売上税額
- (課税売上高×7.8/110×みなし仕入れ率)+(課税売上高×6.24/108×みなし仕入れ率)=仕入れ税額
- 売上税額ー仕入れ税額=消費税の納付税額
軽減税率の適用対象となる取引については「6.24/108」を乗じた金額となっています。
「みなし仕入れ率」は下記のように定められています。
業種に応じて90%から40%までの範囲で指定されています。
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業等)小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) | 80% |
| 第3種事業(製造業等)農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、建築業、製造業など | 70% |
| 第4種事業(その他)飲食店業など | 60% |
| 第5種事業(サービス業等)運輸・通信業、金融・保険業、サービス業 | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% |
事業が2種類以上の場合には、事業の種類ごとに区分し、それぞれで計算する必要があります。
税額計算が簡単になるメリットがありますが、業種によっては原則課税と比較して納税額が高くなってしまう可能性があります。
また逆に、簡易課税をうまく活用して、節税することも可能です。
簡易課税をうまく活用した節税方法
上記でご説明した通り、簡易課税での「みなし仕入れ率」は90%から40%の6段階で構成されています。
課税売上と課税仕入の割合に着目して、節税する方法があります。
例えば、サービス業ではみなし仕入れ率は50%と定められていますが、課税売上に対する課税仕入の割合がみなし仕入率の50%よりも低ければ節税することができます。
簡易課税制度の方が仕入控除税額が大きくなるからです、
逆に言えば、課税売上に対する課税仕入の割合がみなし仕入率の50%よりも高ければ、税負担が増加してしまうことになります。
また、業種ごとに売上を区分することによって節税できるケースもあります。
例えば、サービス業ではみなし仕入れ率は50%ですが、商品の販売であれば小売業となり、みなし仕入れ率は80%と定められています。
このみなし仕入れ率の差によって仕入税額控除を増やすことができ節税することができるのです。
簡易課税から原則課税に変更して節税する方法
簡易課税は、前々年の課税売上高が5,000万円以下の場合に限り適用となるものですが、デメリットもあります。
それは、多額の設備投資が必要となり、課税仕入額が大きくなる場合です。
簡易課税では課税売上だけが計算の対象となり、消費税の還付を受けることができないのです。
しかし、原則課税の申告をしておくことによって、課税仕入額を消費税額の計算に反映させることができますので納付税額を減少させることができるのです。
そのため、このようなケースが生じた場合には、決算時に「簡易課税」「原則課税」の比較をしておき、原則課税が有利の場合には「簡易課税選択不適用届出書」を提出しておくようにしましょう。
消費税の「税抜処理」と「税込処理」に着目した節税スキーム
課税事業者が消費税の経理処理を行うにあたって、「税抜処理」「税込処理」の2つの方法があります。
日常の経理業務では、このどちらかを選んで行うことになります。
税務上においては税抜処理をした方が税法上においてお得となりますが、面倒な作業が多少必要となっています。
どのような違いがあるのかご説明していきましょう。
税抜処理とは
「税抜処理」とは、仕訳処理を行う際に、取引金額に含まれている消費税を分けて処理してしまうという方法です。
上記でご説明した通り、手間は多少かかってしまいますが、税法上の観点で言うと税抜処理を選ぶことをおすすめします。
税込処理とは
「税込処理」とは、仕訳処理を行う際に、取引の総額で処理してしまうという方法です。免税事業者は税込処理で仕訳処理を行います。
中小企業においては、経理処理が簡単になりますので、税込処理が採用されていることが多くなっています。
税込経理と税抜経理での会計処理
損益計算上においては、税抜処理は税込処理と同額になりますが、税法上の処理を行う上でさまざまな点で差異が出てきます。
いくつかの事例をご紹介しましょう。
「交際費課税」については、年間800万円まで損金として認められています(資本金1億円以下の中小企業、大企業の子会社などは除く)。
交際費を経理処理した場合、税抜処理をすれば800万円まで使うことができますが、税込処理をした場合には730万円ほど活用すると税込800万円を超えてしまうことになります。
「減価償却資産」については少額減価償却資産の特例を使った場合、30万未満の少額減価償却資産を取得した場合、年間合計300万円までは、全額を経費にすることができます。
税抜処理をする場合には30万円までは経費にすることができますが、税込処理をする場合には、28万円程度で税込30万円を超えてしまうことになるのです。
個人の課税事業者の法人化による節税スキーム
個人の課税事業者の場合であれば、法人化させることによって消費税を節税することが可能です。
法人化して新会社を設立したり、分社化して別会社を設立したような場合には、消費税の納税義務者である課税事業者は
- 前々事業年度における課税売上高が1,000万円以下
- 給与の支払い合計額が1,000万円以下
※資本金1,000万円未満の中小企業の場合
上記の通り、開業した年度とその次の年度については、納税は免除されています。
そのため、個人事業主で起業し、課税事業者になるような状況になれば1,000万円未満の会社を設立すれば、そこから2年間は納税が免除されることになります。
また、すでに存在している会社を分社化することでも同様に2期分の消費税の納税を免除することができます。
うまく事業を切り離すことで、期間限定ではありますが、かなりの納税額を節税させることが可能となります。
さらに、社員が少ない場合には、社長の役員報酬を調整し、支払額を年間1,000万円以下に調整することにおいても節税に繋がります。
仮決算で中間申告を行う節税スキーム
法人経営を行っている事業者であれば、仮決算によって中間申告での予定納税額を減らすことができるケースもあります。
中間申告とは、半期が経過したときの予定納税のことで、前期の実績をもとに先に納税しなければなりません。
例えば、前期に支払った消費税の合計額が500万円だった場合には、中間申告として半期分の250万円を予定納税しなければならないのです。
しかし、常に業績が順調である訳でもありませんので、この納税によって会社の経営に大きな影響を与えてしまうことも考えられます。
そのため、半期で仮決算を行うことによって納税額を計算しておけば、仮にそこから業績が悪化したとしても、中間申告での納税額を減らすことができるのです。
もちろん、仮決算せずに中間申告をした場合に、税金を払いすぎてしまった場合には、還付金として後から戻ってくることになります。
仮決算した場合も、中間申告した場合でも、納税額は一緒です。
ただ、経営の観点でみると、手元に現金を残しておくことが大切ですから、仮決算は大きな意味があると考えられます。
会社の法人税・消費税の節税スキーム
法人の節税対策に取り組むことによって、消費税の節税対策に繋がります。
専門的な知識が必要になったり、複雑なものも多くありますが、どのような対策があるのか知っておくだけでものちの対策に大きく影響します。
ここでは会社向けの法人税・消費税の節税対策について紹介していきましょう。
未払費用の活用
- 固定資産税
- 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)
- 労働保険(労災保険、雇用保険)
- 従業員給与・賞与(賞与は計上の要件あり)
- 地代家賃
- 借入金利息
- 運賃
- 広告宣伝費
上記に該当する、まだ対価の支払いが済んでいない費用に関しては「未払い費用」として計上することによって節税が可能です。
支払義務が確定しているような場合には、法人税法上、未払費用として計上し、損金算入することができます。
その他、会社の法人税・消費税の節税スキーム
- 1年以内の短期前払費用の損金処理
- 事務用品など消耗品の一括購入の損金処理
- 売れ残りの評価減
- 所有する有価証券の評価損
- 不良債権の貸倒損失
- 値下がりしたゴルフ会員件の売却による損失
- 会社の創立費や開業費を任意に償却する
- 交際費を会議費にして損金算入する
- 社員旅行やレジャークラブの会員費、永年表彰の記念品など
- 従業員の資格や免許取得の奨励
- 旅費規程により旅費・日当の支給、など
その他、上記のような節税対策に取り組むことも可能となっています。
派遣会社や外注の利用
派遣会社や外注を利用した場合の費用は、派遣会社などに消費税分を含めた報酬を支払うことになりますので、節税に繋がります。
例えば、売上の300万円に対して、100万円の外注費が発生した場合、差し引き200万円に対してのみ消費税がかかることになります。
同じ人件費でも、従業員に対する給料の場合には、経費算入できるものの、上記のように消費税まで減らすことができないのです。
課税取引と非課税取引を用いた節税スキーム
世の中のサービスには非課税となっているものがあります。
「消費に対する税」という性格、また社会政策上の配慮によって非課税となっているのです。
ここでは課税取引と非課税取引に着目した節税方法について見ていきます。
消費税がかからないもの
一部対象となっていないサービスがあり、医療や福祉、教育などをはじめとして、土地の譲渡や貸付、有価証券、郵便切手、商品券、埋葬料などは非課税となっています。
「土地」のように消費されるものではないものや、医療や福祉、教育など社会政策上の配慮によってかからないものもあるのです。
さらに、事業として提供されている製品やサービスに課税されるものですから、逆に言えば事業ではない売買に対しては課されることはありません。
例えば、私物を買取ショップやオークションなどを活用して売却した場合、その金額に対して消費税が課されることはありません。
あくまで消費税は「事業者」の製品やサービスに課される税金だからです。
ただし、個人でも売買を繰り返して、継続的に収益を得ているような状況であれば、事業者であるとみなされて、消費税が課される可能性は否めません。
収入印紙の購入
収入印紙は郵便局で購入すると非課税での販売となっていますので消費税を支払うことはありませんが、チケットショップなどで購入すると支払いの中に消費税が含まれていることになります。
これは収入印紙の非課税販売が「郵便局等」と限定されているからであって、チケットショップのような営利企業には適用となりません。
そのため、チケットショップで収入印紙を購入した場合には、購入金額に含まれている消費税を預かり消費税から差し引くことができます。
寄付
寄付については非課税なので消費税を減らすことはできませんが、物品で送った場合には購入の際に消費税を支払っていることになりますので消費税を減らす効果があります。
これは寄付だけではなく、お見舞い品についても同じように扱うことができます。
また地域のお祭りで寄付金を支払うような場合は、企業の名前が提灯に掲載されるような場合には広告代として扱われることになります。
そのため、預かり消費税を減らす効果があります。
正しく節税するためには、専門家に相談しましょう
無駄にお金が出ていかないように利益や資産を守るためには、社長ご自身が自分で調べたり考えたりすることも大前提として重要ですが、知識・経験の豊富な専門家の力を借りることが大切だと私は考えています。
現在の税理士さんに対して、
・顧問料が高い
・訪問頻度が少ない
・提案やアドバイスが少ない
・相性が悪い
・自社の業界に疎い
・年代があわない
などのお悩み・ご不満を抱えている方は、完全無料で何度でも利用できる税理士紹介サービス『税理士ドットコム』で新たな税理士を探してみてはいかがでしょうか?
「弁護士ドットコム」や「クラウドサイン」で有名な、東証マザーズ上場「弁護士ドットコム株式会社」が14年以上運営しているサービスです。
登録税理士 全国5,900名以上、累計実績 153,000件以上と圧倒的な実績です。
紹介された税理士と契約すると、税理士側が税理士ドットコムへ手数料を支払う仕組みなので、税理士を紹介してもらう社長側は最初から最後まで完全無料です。
税理士ごとに得意・不得意や特に強い専門分野など分かれるそうですが、顧問料なども含めて、ちょうど求めているタイプの税理士を自力で探そうと思ったら大変ですよね。
完全無料で何度でも利用できて、利用ユーザーのうち71.4%が顧問報酬の引き下げに成功しているとのことなので、試してみる価値はあります。